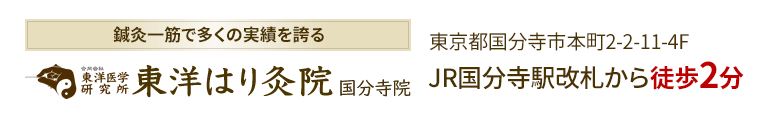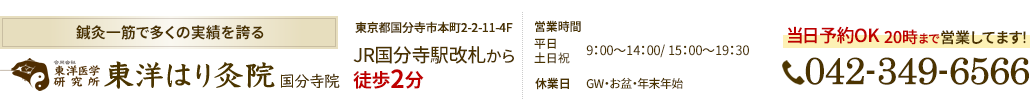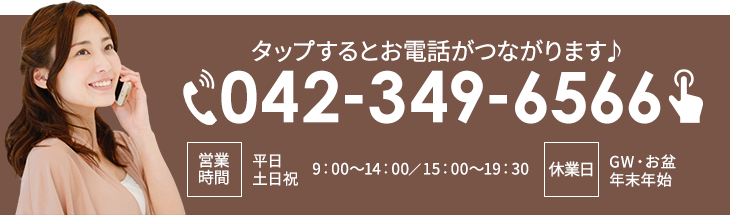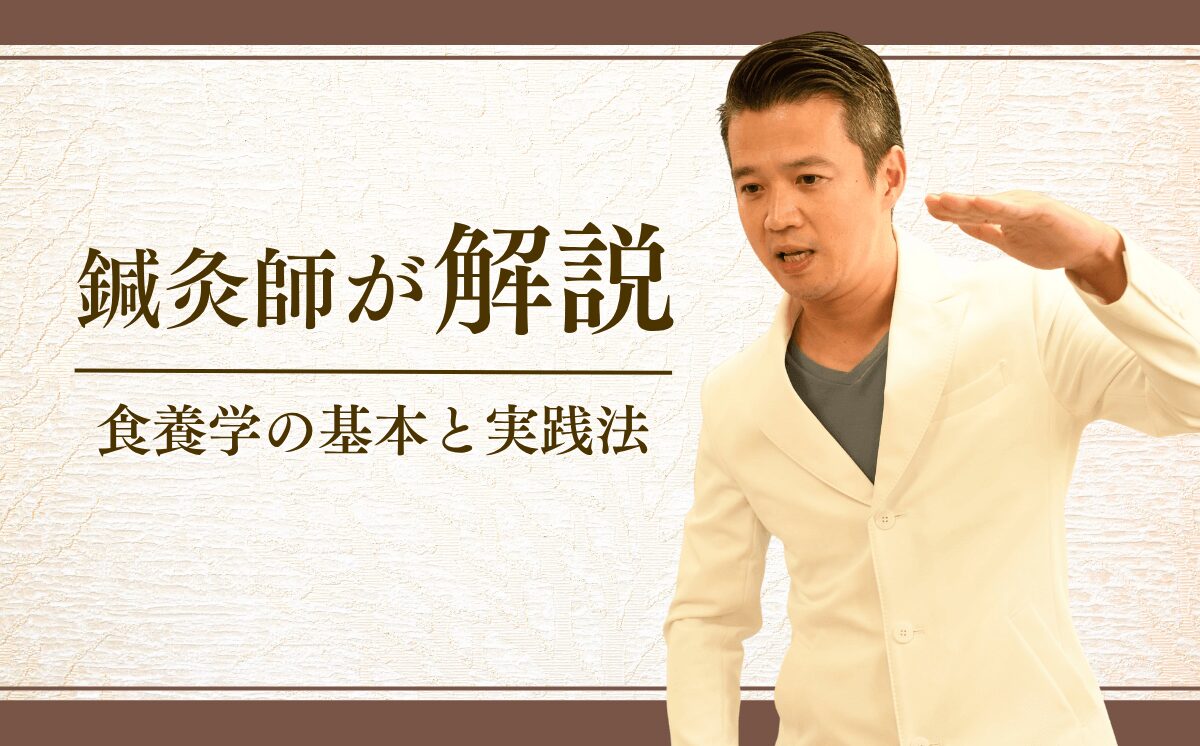
身体によい食べ物と聞くと、ビタミンやミネラルなどの栄養素を思い浮かべる方が多いでしょう。これは主に現代栄養学の考え方ですが、実はこの栄養学が生まれた背景には意外な事実があることをご存じでしょうか。
一方、東洋医学には食養学という独自の考え方があり、その名の通り“食べ物を通して身体を養うこと”を目指します。
本記事ではこれら2つの食に関する考え方を比較し、いつまでも健康な身体でいられるための食生活についてご紹介します。身体によい食事を知りたい方は、ぜひご覧ください。
現代栄養学の背景と問題点

現代栄養学は、20世紀初頭にドイツで体系化されたのちに日本に導入されました。そのルーツをたどると、第二次世界大戦中の軍事目的と深く関わっていることがわかっています。
当時は兵士の身体を大きくして凶暴性を高めるために、動物性タンパク質つまり「肉」を積極的に摂るよう指導していました。しかしドイツと日本では、気候、風土、伝統的な食文化のすべてが大きく異なります。
ドイツで生まれた栄養学が日本人の体質に合わせてアレンジされることなく導入された結果、生活習慣病が低年齢化し、多くの人が不調を抱えるようになったと考えられています。
現代栄養学では、特定の栄養素を摂取することに着目しています。そのため、極端な話、栄養素さえ摂れればそれでよいのです。それが加工食品やサプリメントであっても、はたまた遠く離れた国から運ばれてきたものや農薬が含まれたものであっても、関係ないのです。しかし、本当にそのような考え方で健康な身体は作れるのでしょうか。
東洋医学による「食養学」の考え方とは?

一方、数千年の歴史を持つ東洋医学の食養学は、「食べ物によって体を養う」というのが根本的な考え方です。食養学には現代栄養学にはない深い思想や知識が込められています。
1.身土不二(しんどふじ)
「身土不二」とは、人間の身体とその土地の環境は切り離せないという考え方です。つまり、日本人であれば日本の国土で育った旬のものを食べることが、身体にとってもっともよいということですね。
地球の反対側で育った食べ物は異なる気候や風土の中で育っており、それらを食べると体内のバランスが崩れてしまう可能性があります。自給率の問題はありますが、できる限り国産で旬の食材を選ぶことが大切です。
2.一物全体(いちぶつぜんたい)
これは食べ物を丸ごといただくことで、その食べ物が持つ「陰」と「陽」のバランスすべてを取り入れることができるという考え方です。例えば、野菜は皮ごと、魚は骨や内臓まで、小魚なら頭からしっぽまで丸ごと食べるのがよいとされています。
大きな魚の切り身は「部分」ですが、小魚は「一つの命」として全体をいただきます。同じ動物性タンパク質でも「命」をいただく方が、断然身体にパワーをみなぎらせることができるでしょう。
また、食べ物の外側には身体を冷やす陰の作用が、中心部には身体を温める陽の作用があることが多く、何でも丸ごと食べることで自然と栄養バランスのとれた食事が叶います。
3.季節のものを食す:陰陽のバランスを整える
旬のものを食べることも食養学では重要です。例えば、夏に旬を迎えるトマトやキュウリは体を冷やす作用があり、体内にこもる熱を冷ましてくれます。逆に、冬に旬を迎える食材には身体を温める作用があり、身体を温めてくれます。
季節外れの食材や熱帯地方の食材を冬に食べると、身体が冷えすぎて体調を崩す原因になることがあるため、できるだけ避けた方がよいでしょう。
食養学による「元気が出る食事」の具体例

食養学を用いた元気が出る食事の一例をご紹介しますので、ぜひ取り入れてみてくださいね。
主食は玄米などの穀物を中心に、食事全体の約6割を目指すのが理想的です。日本で古くからある味噌汁や納豆などの発酵食品も、腸内環境を整え、体質改善に役立つと言われているため、ぜひ食卓に取り入れていただきたい食材です。
また、特に牛肉は内臓に負担をかけると言われているため、鶏肉など比較的消化しやすいものを中心に、適量を心がけましょう。日ごろの水分補給は水か無農薬の三年番茶にすると、健康な身体を作ることができますよ。
食養学を取り入れていつまでも健康的に

食養学は、何千年もかけて先人たちの経験と観察によって培われてきた事実の結晶です。科学的に証明できないからと否定されがちですが、それは現代科学が東洋医学の根底をまだ解明しきれていないからかもしれません。
病気を寄せつけず、真に健康な状態を維持するためには、食事が大切です。食べるものを自由に選べる現代だからこそ、食養学の考え方を取り入れることで健康への道しるべとなるでしょう。